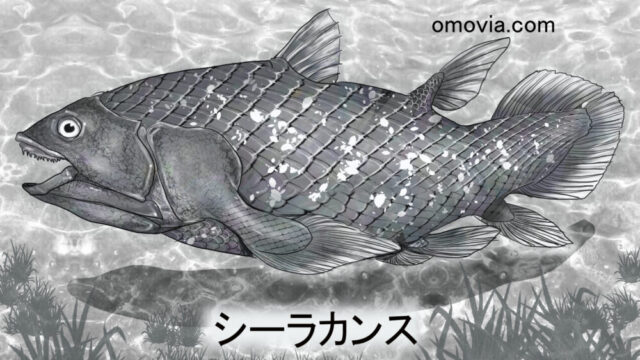北海道が誇る日本最大級の鶴「タンチョウ」をご存知でしょうか。
古くから国を代表する「ツル科ツル属」の鳥として知られており、旧千円札紙幣には裏側の透かし部分を対称に、2匹のタンチョウが描かれていることでも有名です。
このタンチョウですが、その歴史は非常に受難に満ちています。
遡る事江戸時代には、北海道全域に生息しており、その姿は何と関東地方や全国各地で見ることが可能でした。
ただ明治維新以降後の新政府の北方開発計画のスタートと同時に、蝦夷地開拓者による乱獲が始まります。
1920年に「完全絶滅」との認定を受けますが、1924年に釧路湿原にて10数羽の個体群が奇跡的に発見されたのです。
この僅かな個体群からタンチョウはいかにして復活の道を遂げたのでしょうか。
それではまず、タンチョウの生態に着眼しお話しさせて頂きます。
「タンチョウ」とは
“タンチョウ”は正確には「鳥網ツル目ツル科ツル属」に分類される、列記としたツルの仲間です。
頭部てっぺんには羽毛が生えておらず、赤い地肌が露出しており、さも冠を被っているような容姿が印象的です。
この赤みの正体はタンチョウの血液そのもので、僅かながらですが周辺部位には黒い羽毛が生えていることが見てとれます。
タンチョウは漢字で「丹頂」と表記され、花札などでお馴染みの「丹」は「赤い」という意味を持っています。
特徴的な赤頭が「タンチョウ」の語源になるという訳です。
この赤い地肌は興奮すると大きく隆起し、オス同士の縄張り争いや、天敵への威嚇行動に用いられます。
体色はやや地味な白と黒ですが、この対称色のコンストラストが本種を逆に非常に際立たせていると言っても良いでしょう。
タンチョウはその羽と頸部・脚部のみ黒色に染まっています。
日本におけるツルのイメージとなると、このタンチョウを連想する方がほとんどなのではないでしょうか。
また通常鳥類は飛行をする特性上、骨の内部がスカスカであり餌の消化が異様に早いなど、体重を可能な限り減少させる動物です。
ところがタンチョウの体重は個体差にもよりますが、4kg~11kgまでに及び、大きな個体となると実に12kgにも達します。
体重に比例して当然その身体も巨大になります。
タンチョウはその全長が実に120cm、一つの翼の長さは60数cm、そして鳥類が最も大きく見えると言われる「翼開帳時の長さ」は何と240cmに及びます。
しかも全長は脚部を加味しない、くちばし先端から尾羽までの長さなので、立ち上がった際は数字以上の威圧感を受けることでしょう。
2021年現在、世界のタンチョウは約3000羽が東アジア各国に生息していると言われていますが、その実に半分以上の1500羽超が、北海道釧路湿原を中心に分布しています。
タンチョウがその住処として好むのは、前述の釧路湿原の様な湿地帯がほとんどですが、湖や沼・河川など個体数の増加と共に目撃される場所も多様になっています。
しかし近年は個体数の伸びに反比例するように、開発や汚染などで湿地帯が減少しているという問題が浮上しました。
そのため通常ではありえないような場所、例えば民家近くや人の集落などに降りてくることも多くなり、交通事故死などに巻き込まれてしまうという悲しい現状も起こるようになってしまいました。
この問題はただ単純に絶滅寸前の動物の個体数を増やすだけが「保護活動」ではない、という問題点を広く保護活動に警鐘した大きなケースとなります。
こちらについては後述の項で詳しく話をさせて頂きます。
タンチョウの繁殖は完全な一夫一妻制です。
しかも非常に愛情深い鳥ということが周知されています。
過去にはペアの亡骸が朽ち果てるまで傍らを離れなかったという観察例や、交通事故により保護施設で手当てを受けたタンチョウがそこで相方を見つけ、死ぬまで寄り添いあったという記録が残っているほどです。
その様な性格をしているからこそ、人間側の都合で人工繁殖が容易に行えません。
子孫を残すのは主に、北海道の厳冬期の2月から初春にかけての4~5月頃です。
この時タンチョウは実に2~8平方kmの縄張りをつくり、安全に産卵・ヒナの育成ができる環境づくりに努めます。
比較対象として有名な東京ドームは概算で289.61平方kmですので、概ねドーム全体の1/150~1/36ほどです。
タンチョウの繁殖や子育てはこの様に、かなり広大な土地も必要となる上に、充分な水場である「湿地帯」が必要不可欠になってくるんですね。
この様に産卵・繁殖・子育ての大半は湿原地帯で行われます。
繁殖期が訪れると、タンチョウの夫婦は仲睦まじく平地に、木の枝や草木・枯葉などを積み上げていき皿状の巣を作ります。
この巣は鳥類が作る「皿巣」としてはかなり巨大になり、30~50cm程の高さと1.5~2mほどの大きさにまでなるのです。
そこに成人男性が両手で抱えて余りあるほどの大きさの卵を産みつけるのですが、その数はほぼ1個、多くて2個が限度と非常に少産です。
湿原の減少と共に繁殖地も多様化しており、河川の三角州や飛び地的な湿原での繁殖例も記録されているのですが、やはりその様な場所でのヒナの生存率は湿原での子育てと比較し著しく落ちてしまいます。
抱卵する期間は1カ月間にも及び、オスメス交互に交代で卵を暖めあいます。
一月後に生まれるヒナは親鳥とは似ても似つかぬヒヨコのような綿毛に全身を包まれていて、孵化直後から自分の足で歩くことができます。
親の後を追いかけ、親鳥が捕まえた獲物を貰いながら家族で過ごし、時には他の複数の家族も加えた大きな群れ内で育つ姿も目にします。
この様に社交性を身に付けたヒナは生後100日くらいには、綿毛がすっかり羽毛に置き換わり、空を飛ぶこともできるようになります。
ただこの時、ヒナが2羽の場合の完全生存率はかなり低くなることが知られており、高確率で1羽しか成鳥になることができません。
この点は長年の謎になっていますが、先に孵化したヒナとの成長差や、そのヒナの攻撃性が強くなることが確認されています。
ヒナ同士が争い合い、力の強いヒナの方が兄弟を蹴落とし生き残る習性があるとも言われていますが、現状では本当の所は定かではないのです。
親鳥はもちろん、ヒナも産まれたての頃から様々な湿地帯の生き物を捕食することが可能です。
タンチョウの餌は湿地帯ならではで、非常にバラエティーに富んでいます。
エビやカニ等の甲殻類から始まり、ドジョウやワカサギ等の魚類・カエル・クモ・各種昆虫・貝類、果てにはヨシキリなどの他の鳥類のヒナ・小型のネズミまで捕食してしまいます。
植物食の一面も持っており、セリ・ナズナ・ゴギョウなどの七草類や湿地帯につきもののアシやガマの新芽・ミズナラなどの果実食も行い、すくすくと育っていきます。
そしてタンチョウはその寿命の長さも特筆するべき点になります。
よく「鶴は千年、亀は万年」と言われ長寿の代表格と言われており、これは流石に誇大表現なのですが、タンチョウの寿命は自然界で平均30年、飼育下で平均50年にも及ぶのです。
飼育下個体の長寿記録は65歳であり、これは他に長寿として知られる鳥類のインコ・オウム類に引けを取りません。
この様に日本を代表するツルの範疇に収まらない鳥類、それがタンチョウという貴重な生き物なんですね。
「タンチョウ」の分布・生息地
ではタンチョウは日本の北海道以外にはどのような国に生息しているのでしょうか。
タンチョウは島国である日本を除けば、他の生息地はユーラシア大陸東部…つまり東アジア周辺の各国と広域に渡っています。
北限生息地はロシアになり、南限は朝鮮半島の大韓民国です。
他にも中国・北朝鮮の個体群も広く知られています。
大きく異なるのは日本以外のタンチョウは渡り鳥という点です。
大規模な繁殖地として中国とロシアをまたぐアムール川(中国では黒河・黒水と呼ばれています)が世界的に有名であり、繁殖期が終わると越冬のため中国南部や朝鮮半島に渡ります。
国内に於いては実に全世界のタンチョウの約半分の個体が留鳥として、そしてその大多数が「釧路湿原」を中心に生息しています。
主に北海道の東部、道東中心に生息しており、かつて個体数の大規模減少の際は釧路湿原でしか見ることができなかったので、タンチョウ=釧路湿原と考えている方も少なくはありません。
しかし最近では個体数の増加と共にその生息地も釧路湿原限定ではなく、多岐に渡るようになりました。
根室管内に集中するのですが「霧多布湿原」「風連湖」での生息・繁殖例も観察できるようになり、2010年代には遂に道北の湿原・酪農地帯で有名な「サロベツ原野」での報告例も上がったのです。
その後も北海道幌延町・旭川町の沼に親子連れが訪れたりと順調に生息域の拡大が確認されています。
ただ一つ懸念材料があり、それは前述した個体数と好適環境の齟齬についてです。
本来、サロベツ原野の様な道北地方はタンチョウにとっても過酷な寒さの環境であり、子育て等は季節を選ばなくてはいけません。
この様なアンバランスな状態が、現状におけるタンチョウの保護活動の最大の課題となっています。
「タンチョウ」が絶滅危惧種となった理由
かつては北海道以外でも目にすることができたツル、それがタンチョウです。
江戸時代の資料を元に調べてみると北海道の留鳥個体群以外にも、ユーラシア大陸から渡り鳥として来鳥する越冬個体群が東北地方・関東、そして中国地方・九州にまで渡来していたという記録が残っています。
なぜタンチョウは絶滅危惧種と呼ばれるのでしょうか。
それには人間社会の移り変わり、とりわけ政治面が深く関わります。
江戸時代から明治維新を経て新政府が樹立された時に、一番行き場を無くしてしまったのが武士です。
割をくらった武士という階級は、生き抜くために新政府による新しい日本づくりの先駆者とならざるを得ませんでした。
当時で言う蝦夷地、つまり北海道への移住・開拓もその一環です。
またこの時代は貿易などで積極的に銃火器を欧米国家から輸入しています。
ここからタンチョウの悲劇が始まります。
タンチョウは食用には向いておらず、その肉はすすんで食べるようなものでは決してありません。
しかしそれは今の時代だからこそいえることです。
北の大地であり極寒の環境である北海道において開拓者のタンパク源は、身体が大きく肉量もあり容易に捕獲できるタンチョウに必然的に目が向くこととなります。
こうして大規模な狩猟と北海道の開拓事業が並行して行われる事態になり、タンチョウは瞬く間に姿を消していったのです。
一部ではその大きくて長い羽を加工し、郷土土産としても収入を得ていました。
こうして人間に翻弄されたタンチョウは、急速にその姿を消していくのです。
刀から銃火器、湿原の水田への転用、人間側から見れば技術の進歩で喜ばしいことですが、タンチョウにとっては次々に殺戮され安寧の湿原を踏み荒らされるという最悪の循環に陥ったのです。
日本各地でも似たような事態に陥り、渡り鳥として飛来するタンチョウは完全に消え去ってしまいました。
「乱獲」と「湿原の消失」、この二つがタンチョウにとっては致命的でした。
こうして北海道の留鳥群も完全絶滅したのです。
ところが時代が進み大正に入ると、大正13年(1924年)に釧路湿原の鶴居村にて10数匹のタンチョウが再び目撃される事態が起こります。
この完全絶滅からの復活の話が広まり、タンチョウ保護の取り組みが急速に加速化する訳です。
「タンチョウ」の保護の取り組み
タンチョウの保護活動はこの1924年の発見がターニングポイントと言えます。
当時の国際情勢の緊張下、そして日本人が決して豊かとはいえない時代背景にもかかわらず、ことタンチョウ保護のケースは非常に迅速かつ柔軟でした。
時代は遡りますがタンチョウの減少が見られた1800年代に、当時の北海道庁は既に狩猟禁止の措置を取っています。
1890年には生息域を禁猟区にし、1892年には日本国内でのツル狩猟が全面禁止となったのです。
国内の少数動物に対する処遇としては異例の早さでした。
戦前の1935年にはタンチョウ・生息地のセットで天然記念物にすら指定されているのです。
そして戦後間もない1952年には特別天然記念物にまで格上げされました。
1967年にはタンチョウそのものが特別天然記念物に制定されます。
ですが制度を設けたところで実効性が伴わなくては意味がありません。
当初は餌となるドジョウの放流や、植物の樹林が盛んに行われましたが、残念ながら個体数が上向くことはありません。
餌を奪う競合動物の駆除や、生活の場である湿地帯の保持など、あらゆる手を尽くしてもタンチョウの減少傾向は止まりません。
ところがここで意外な出来事が起こります。
飢えたタンチョウが、畑に干してあるトウモロコシを口にし始めたのです。
これをヒントにトウモロコシの餌場を作ると、瞬く間にタンチョウの数が増えていきます。
この活動は現在でも行われていて、人との距離を取った餌場に提起的にトウモロコシ等を給餌し、タンチョウが冬を乗り切る貴重な栄養源となっているのです。
タンチョウ現象の一番の要因は、湿地帯の減少による冬場の餌の確保が困難になったことに起因していました。
その後、自然保護団体による湿地帯の買い上げなどのナショナルトラスト運動や、釧路湿原近くの旧阿寒町・鶴居村などの地元の方々による給餌活動の継続が拍車をかけ、遂には1500羽にまでの回復を遂げたのです。
今日ではタンチョウが渡り鳥として生息する各国も、日本に習い積極的な保護活動を行っています。
まとめ
この様に一見大成功に終わったように見えるタンチョウの保護活動ですが、じつはまだ様々な問題点を抱えています。
その一つが種の多様性です。
僅か10数話から回復したタンチョウは、かなり血が濃く遺伝的な近縁種が増えるのではないかと懸念されています。
そして二つ目は人間なしでは生きにくい状況になってしまった事です。
本来、野生動物に餌を与えるのは禁則行為なんです。
タンチョウが持つ野生下での捕食能力も奪う上に、裏を返せば人間が給餌を取りやめると、個体数が減少してしまうという構図も成り立ってしまったからです。
近年環境省は餌場を徐々に減らしていく方針を示しました。
それはある意味正解でしょう。
ただ同時進行として湿原の保持、そして拡大を並行して行わなければいけません。
タンチョウが真に野生に帰り、自らの力で生き抜いていく環境。
それを今一度考えるべき時が来ているのではないでしょうか。