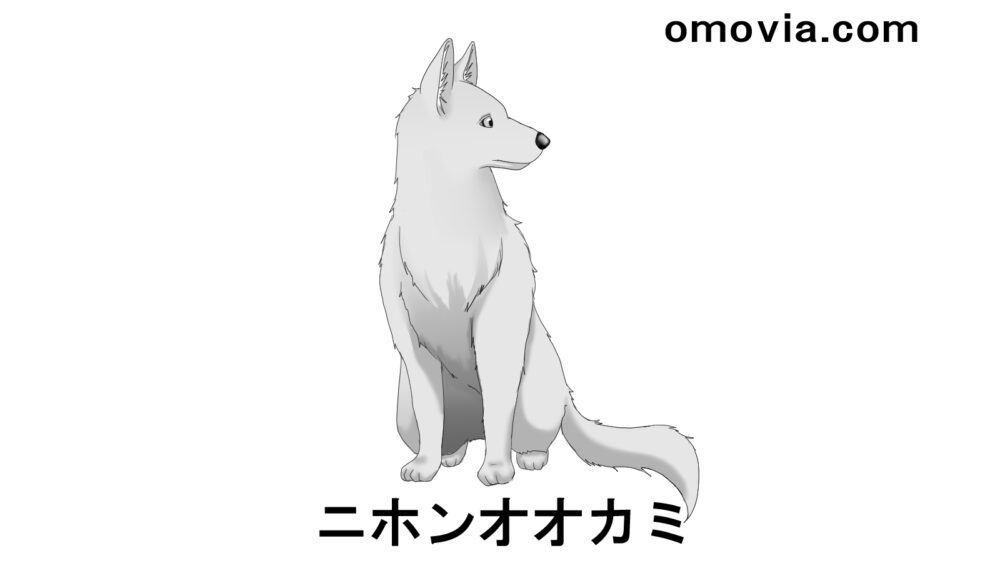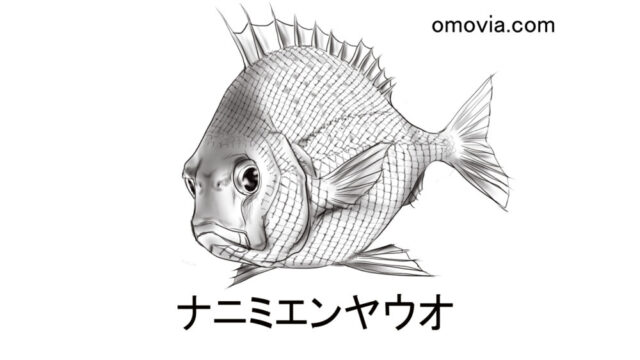ニホンオオカミは明治中期ごろまで本州以南に広く分布していたオオカミで、確実な情報としては、1905年に奈良県東吉野村で捕獲された個体を最後に姿を消しました。
環境省レッドリストでは過去50年間生存の確認がなされない場合、その種は絶滅したとされるので、ニホンオオカミは絶滅種となっています。
分類上は、食肉目イヌ科イヌ属に分類され、ジャッカルやコヨーテと同じなかま(属)です。
ニホンオオカミの大きさは1メートル前後、肩高55センチメートルで、推定体重は15キログラムと、大陸のオオカミよりも小さく中型の日本犬ほど。
しかし、同サイズのイヌよりも四肢は頑健で長く、脚力も強かったと言われています。
外見上の最大の特徴は顔の凹凸で、イヌには吻と呼ばれる頭頂部から鼻にかけてのくぼみがあるのに対して、ニホンオオカミではくぼみはなく平らです。
また、耳介が短いのもイヌとニホンオオカミを区別する大きな特徴の一つです。
その他にも先端が丸みを帯びる常に垂れた尾をもつ、耳介後側と四肢の外側が赤みがかった毛色を示している、などの特徴をニホンオオカミはもっています。
ニホンオオカミの起源と分類については、大陸のハイイロオオカミと同種の別亜種と考える説と、完全な別種と考える説があり、未だに決着していません。
ニホンオオカミと大陸産のハイイロオオカミの間でも、頭骨に複数の相違点があることが報告されており、ニホンオオカミを独立種とみなす根拠となっています。
最近ではニホンオオカミの起源について、DNAを用いた遺伝学的調査により重要な知見が得られています。
ニホンオオカミのミトコンドリアDNAを解析した岐阜大学の石黒教授らは、かれらの遺伝的多様性が低いことを指摘し、ユーラシア大陸由来のハイイロオオカミとは独自の進化を遂げた地方集団であると述べています。
ニホンオオカミとヒトとの関わり
ニホンオオカミは、本州・四国・九州に広く分布していましたが、本格的な学術調査が行われる前に絶滅してしまったため、分布や生態については不明な点が数多く残されています。
そのため、ニホンオオカミがどのような暮らしを営んでいたかについては、古文書や神社仏閣の伝承などにより推測されてきました。
オオカミは西欧諸国では家畜を襲う害獣として駆除されてきましたが、日本ではシカやイノシシなどの農作物を食べる草食獣を餌としたため、農民にとっては大変ありがたい存在でした。
そのため、多くの神社でニホンオオカミを守り神として祭っていて、秩父の三峰神社などではお札(おふだ)のデザインにもオオカミが使われています。
また、地方によってはニホンオオカミの頭骨や毛皮、牙などが魔除けとしての意味をもつこともあったようです。
最近も、徳島県国府町の民家で、神棚の木箱からニホンオオカミの頭骨が発見され話題となりました。
さらに最近になって、岩手県大槌町で江戸時代から保存されている「狼酒」に含まれる骨片が、ニホンオオカミのものであることがDNA診断によって判明しました。
狼酒は心臓病の秘薬として受け継がれていたそうなので、神格化されたオオカミの力で病気を治したいと考えたのかもしれません。
このようなオオカミ信仰は他にも沢山知られており、オオカミを恐れると同時に、神秘的な存在として敬っていたことがうかがい知れます。
一説によると、オオカミという名前は、「大神」として人びとが奉ったことが起源ではないかと言われています。
狼信仰の反面、人里では馬などの家畜や、ヒトがニホンオオカミに襲われる事例も少なからずあったようです。
江戸中期(1709年)の尾張藩では、3月中にオオカミに24人が襲われ、そのうち16人が死亡し、8人が傷を負ったことが記録されています。
尾張藩の3月だけでこの数字ですから、日本全国では年間数千人の犠牲者が出ていた可能性があります。
実際には、ニホンオオカミは山間部に広がる草原にある岩穴に巣を作り、2~10頭程度の小さな集団で行動していたため、ヒトとの遭遇はそれほど多くなかったと想像できます。
それにもかかわらず、狼信仰が日本中に広まっているのは、二ホンオオカミに対しての恐怖心が根底にあり、姿は見えずとも遠吠えは聞こることによる神秘性が影響したのかもしれません。
その遠吠えは良く響き、障子を振動させたほどであったということですから、人々に畏怖の念を抱かせたことは間違いないでしょう。
ニホンオオカミが絶滅した原因
このように、ヒトとおおむね良好な関係を築いてきたニホンオオカミですが、江戸時代後期になると状況は一変します。
1732年頃にニホンオオカミの間で狂犬病が流行し、罹患したオオカミによるヒトの襲撃が増加しました。
オオカミに咬まれたヒトが苦しんで死んでいく様を見て、狼信仰は消え去り、ニホンオオカミは一転して忌まわしい存在となりました。
そのため、人びとはニホンオオカミを次々と撃ち殺し、咬まれれば発病率100%の狂犬病から逃れようとしました。
ニホンオオカミが絶滅への道をたどった別の理由として、ジステンバーの流行があります。
明治時代には西洋犬の導入が始まったこともあり、それに伴いジステンバーなどのウイルス病が流行しました。
ニホンオオカミはジステンバーに対する抵抗力がなかったため、瞬く間に病気が広まったと考えられています。
さらに、明治期は日本中で山林の伐採と、肉食文化へ転換するための家畜導入が始められた時代であったことも見逃せません。
山林の減少によって、二ホンオオカミの獲物となるシカなどの数は減少し、生息地は狭められました。
さらに、腹をすかせたオオカミは家畜を襲うことが多くなったため、害獣として駆除される機会が増えていきました。
これら複数の要因のうち、どれが最もニホンオオカミの絶滅にとって重要であったかは、今となっては知る由がありません。
今から150~200年前は、日本を含む世界中で野生動物を殺すことに殆ど抵抗がなかった時代だったので、ニホンオオカミが絶滅へと向かったのは必然であったのかもしれません。
ニホンオオカミ生き残りの可能性
公式には、1905年(明治38年)に奈良県東吉野村鷲家口で捕獲された若い雄の死体が、最後のニホンオオカミということになっています。
この死体は腐敗が進んでいたため、毛皮と骨格のみがイギリスへ送られ、現在も大英博物館で保管されています。
しかしこの定説以外にも、その後もニホンオオカミが生きていたと思われる情報があります。
一番有名なのが、1910年に福井県で捕らえられた個体で、はく製にもされたましたが、残念ながら1945年の戦火で焼失してしまいました。
福井市立郷土歴史博物館に残されている写真を見る限りでは、外見上の特徴の多くはニホンオオカミと合致しています。
その他、物証がない目撃例や、遠吠えを聞いた等の情報は、現代に至るまで数多く報告されていますが、その多くは野生化した犬を誤認したと考えられます。
しかし、現代でもニホンオオカミの生存を信じ、調査・研究を地道に続ける人々は存在しています。
そんな団体の一つである「NPO法人ニホンオオカミを探す会」では、奥秩父を中心に70台の監視カメラを設置して、ニホンオオカミが生存している証拠を探索しています。
1996年には「探す会」八木博氏が、それらしい動物の撮影に成功しています。
さらに2000年になって、大分県祖母山山麓で、柴犬程度の大きさの動物が撮影され、ニホンオオカミの可能性が検討されました。
これらの写真の鑑定を依頼された動物学者の今泉吉典氏は、写真に写った動物は、ニホンオオカミの標本が持っている特徴を余すところなく備えていて、ニホンオオカミである可能性が高いと述べています。
さらに、前出の八木氏は、動画に記録されていた動物の咆哮に関して、音響データを日本音響研究所に持ち込み、イヌ(四国犬)、動物園で飼育されているオオカミ、雄シカの周波数と比較しました。
その結果、シンリンオオカミの咆哮と極めて類似していることが判明し、画像に写った動物がオオカミである可能性は高いとしています。
それらが本当にニホンオオカミであるかどうかは、死体が発見され、骨格やDNAを用いた詳細な調査を経てからでないと確実なことは言えません。
今隆盛の比較ゲノム解析を用いれば、ニホンオオカミであるか否かだけでなく、日本にもともといたイヌとの関係性も明らかになるかもしれません。
まとめ
全く別のアプローチから、ニホンオオカミの復活を試みる人たちがいます。
理化学研究所・発生再生科学総合研究センターの若山照彦博士らは、ニホンオオカミのはく製からクローンを発生させることに挑んでいます。
はく製から分離した細胞の核を取り出し、イヌの卵子に移植することによって、クローン胚を作成する計画です。
ただ、絶滅種を人工的に復活させることは理論的には可能であっても、技術的にはたいへん難易度が高く、まだ時間がかかりそうです。
人間の身勝手で神格化され、その後害獣として駆除されて絶滅したニホンオオカミに対して、贖罪の気持ちから、どうにか復活してほしいという思いは、多くの人々が抱いているのではないでしょうか。